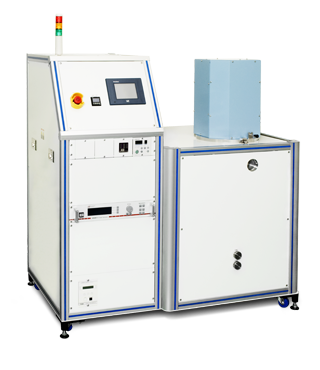半導体とは簡単に言うと、導体・絶縁体の中間に位置し、電気を通したり止めたりできる特別な物質のことです。
例えば、導体である金属は電気を通します。しかし絶縁体であるゴムは電気を通しません。一方で半導体は、この金属とゴムの中間みたいな性質を持っているわけです、
この半導体、ただ電気を通すだけでなく、電気の通り道を細かく調整できるところが特筆すべき点です。
例えば、水の流れを蛇口で調整するように、半導体では電気の流れを調整できますから、この性質を利用して、コンピューターやスマートフォンの中にある小さな部品に応用されています。半導体は、私たちの生活を豊かにするたくさんの製品を作るために欠かせないもの。小さな部品だけど、すごい働きをしています。
この記事では、半導体の基本的な知識を解説するとともに、現代のどんなところに活かされているのかご紹介します。
これまでも、これからも、半導体は発展し続けます。半導体の発展がすなわち現代の生活の発展といっても過言ではありません。
半導体の特徴:3つの役割
半導体には主として3つの役割に整理できます。
1. 電気の流れをコントロールする
半導体は、電気を通したり止めたりすることができます。この機能を活用すると、
- 電気のオンオフ: 電気をつけたり消したりする
- 電気の通り道を決める: 電気を通したいところだけに電気を流す
といったことが可能になります。これによって、コンピューターの中の計算や、家電製品の動作をコントロールしています。
2. 電気信号を大きくする
半導体は、小さな電気信号を大きくすることもできるんです。例えば、ラジオのアンテナでキャッチした弱い電波も、半導体を通ると大きな電気に変わるので、スピーカーから大きな音が聞こえるようになります。
3. 電気と光を交換する
半導体は、電気と光を交換することもできます。例えば、LED電球は、電気のエネルギーを光に変えて、明るい光を出しています。また太陽電池では、太陽の光を電気のエネルギーに変えて、電気を作り出すことも可能です。
代表的な半導体の種類と働き
集積回路(IC)
たくさんのトランジスタなどを小さなチップにぎゅっと詰め込んだものです。コンピューターの「脳」のような働きをします。
オプト半導体
電気と光を自由に変換できる半導体です。LED電球や太陽電池に使われています。
センサー半導体
温度や光、圧力など、周りの環境の変化を感知して電気信号に変える半導体です。
整流ダイオード
電気を一方向にしか流さない半導体です。整流器や検波器などに使用されます。
ツェナーダイオード
ツェナーダイオードとは、電圧が急に上がったり下がったりしたときに、回路を保護する役割を持つ半導体です。雷や静電気など、思わぬ原因で電子機器が壊れてしまうのを防ぐために使われています。
パワーモジュール
大きな電力を扱うために、複数の半導体を組み合わせたものです。自動車や産業機器に使われています。
MOSFET
電気をオンオフしたり、大きさを調整したりする働きをするトランジスタの一種です。
半導体の仕組み
半導体は、電気を通すか通さないか、その境目にあるような物質です。この性質の鍵を握るのが「バンドギャップ」と呼ばれるもの。バンドギャップは、電子が通れない壁のようなもので、この壁が厚いと電気が流れにくく、薄いと電気が流れやすくなります。
半導体は、このバンドギャップがちょうど良い厚さなので、少し手を加えることで、電気を自在にコントロールできます。そのために使われるのが、P型半導体とN型半導体の2種類です。
P型半導体:電子が足りないから、穴が動く!
P型半導体は、電子が少し足りない状態の半導体です。電子がいない場所を「正孔(ホール)」と呼ぶのですが、この正孔がまるでボールが転がるように、電子と反対の方向に動きます。つまり、正孔が動いているように見えることで、電流が流れているように見えるのです。
N型半導体:電子がたくさん!自由に動き回る
N型半導体は、電子が余っている状態の半導体です。余った電子が、自由に動き回ることができるので、電流を流すことができます。
P型とN型を組み合わせた「PN接合」
P型半導体とN型半導体をくっつけると、面白いことが起こります。この組み合わせを「PN接合」と呼びますが、PN接合には、電気を一方向にしか流さないという性質があります。この性質を利用して、ダイオードやトランジスタなどの電子部品を作ることができるのです。
半導体の活用例
半導体はどんな場面で活かされているのでしょうか。
1. 家電製品を賢くする
冷蔵庫やエアコン、炊飯器など、家電製品にも半導体が使われています。例えば、冷蔵庫の中をいつも一定の温度に保つのは、半導体が温度を測って、冷やしすぎたり温めすぎたりしないように調整しているからです。
2. 車を安全にする
自動車にも、たくさんの半導体が使われています。例えば、車のエンジンをスムーズに動かすために、半導体が重要な役割を果たしています。また、最近の車は、自動運転を目指してどんどん進化していますが、その技術にも半導体が欠かせません。
3. 社会のインフラを支える
電車や飛行機、医療機器など、私たちの生活を支える様々なものにも、半導体が使われています。例えば、電車は、半導体のおかげで安全に目的地まで運んでくれるし、医療機器は、病気の診断や治療を助けてくれます。
半導体の歴史
半導体の歴史は古く、19世紀末の「真空管」にまでさかのぼることができます。半導体が登場したおかげで、たった100年で人類の生活が一変したといっても過言ではありません。
1. 真空管時代と半導体の誕生
真空管は、電子を真空中に放出して電流を流すデバイスです。ラジオやテレビなどの初期の電子機器に広く使われていました。しかし、大きくて壊れやすく、消費電力も大きかった点が課題でした。
1947年、ベル研究所によってトランジスタが発明されました。トランジスタは、真空管に比べてはるかに小さく、消費電力が少なく、信頼性も高かったため、急速に普及しました。
2. ICの発明と集積回路の時代
1958年、テキサス・インスツルメンツのジャック・キルビーによって集積回路(IC)が発明されました。ICは、複数のトランジスタを1つのチップ上に集積したもので、電子回路の小型化と高性能化を飛躍的に進めました。
その後、ICの製造技術の進歩により、ますます多くのトランジスタを1つのチップ上に集積できるようになり、電子機器は小型化・高性能化の一途を辿りました。
3. LSI、VLSIの登場とコンピュータの進化
大規模集積回路(LSI)や超大規模集積回路(VLSI)の登場により、コンピュータの性能は飛躍的に向上しました。
その典型がマイクロプロセッサです。マイクロプロセッサは、コンピュータの中心的な処理装置であり、LSI技術の発展によって高性能化が進みました。パーソナルコンピュータの普及を促し、私たちの生活を一変させました。
4. 半導体の多様化と応用展開
その後もメモリチップ、マイクロコントローラー、センサーなど、様々な種類の半導体が開発されました。
身近な製品への応用でいえば、デジタルカメラ、スマートフォンです。私たちの身の回りの製品には、数多くの半導体が組み込まれています。 IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)といった新たな技術の発展には、高性能な半導体が不可欠です。
半導体の製造過程
1. 設計:まずは設計図を作る
半導体チップを作るためには、まず設計図を作るところから始まります。この設計図は、まるで家の設計図のように、将来のチップにどんな機能を持たせるかを細かく決めていきます。この設計図を元に、フォトマスクと呼ばれる特別なフィルムを作ります。このフィルムに、将来のチップの回路パターンが描かれているのです。
2. 前工程:シリコンウエハに回路を書き込む
次に、シリコンという素材で作られた薄い板(ウエハ)を用意します。このウエハの表面に、先ほど作ったフォトマスクを使って、回路パターンを焼き付けていきます。まるで、お餅に型を押すように、シリコンウエハに回路の型を付けるのです。この作業を何度も繰り返すことで、複雑な回路が作られていきます。
3. 後工程:小さなチップを切り出して完成
回路が完成したシリコンウエハは、小さな正方形に切り分けられます。この小さな正方形一つ一つが、私たちが普段目にする半導体チップです。切り出されたチップは、プラスチックなどのケースに封入され、様々な電子製品に組み込まれていきます。
次世代の半導体
従来、半導体はシリコンという素材で作られていましたが、最近では、より高性能な「次世代半導体」が注目されています。
これまでのシリコン製の半導体は、私たちの生活を大きく変えました。しかし、より速く、より多くの情報を処理するためには、シリコンだけでは限界があるのです。そこで、より優れた性能を持つ新しい素材の半導体が必要になったのです。
次世代半導体に使われるGaN(窒化ガリウム)やSiC(炭化ケイ素)などの材料は、シリコンにはない素晴らしい特徴を持っています。
まとめ
物質の性質を理解することは、まるでパズルを解くようなものです。一つ一つのピース(原子や分子)がどのように組み合わさっているか、そしてそれらがどんな性質を持っているのかを理解することで、新しいものを作ったり、既存のものをより良くしたりすることができるのです。
半導体はその良い例で、トランジスタや集積回路といった現代社会を支える基盤技術が生まれました。物質の性質を理解することは、単に「ものづくり」だけでなく、科学技術の進歩そのものを牽引する力となるのです。物質の性質を深く探求することは、未来の技術革新につながる、とても面白い冒険なのです。
【参考資料】
- 東京エレクトロン株式会社『半導体の歴史』
- HITACHI『半導体とは』
- HITACHI『半導体製造工程』
- 吉田SKT『半導体とは?種類や役割、使用例などを簡単にわかりやすく解説』
- https://www.y-skt.co.jp/magazine/knowledge/guide-semicon/
- ShinDengen『半導体の種類について|パワー・ロジック半導体の違いも解説』
- coevo『次世代半導体とは?日本が世界トップに返り咲くカギとなるか』
- 文部科学省『次世代半導体のアカデミアにおける研究開発等に関する検討会』