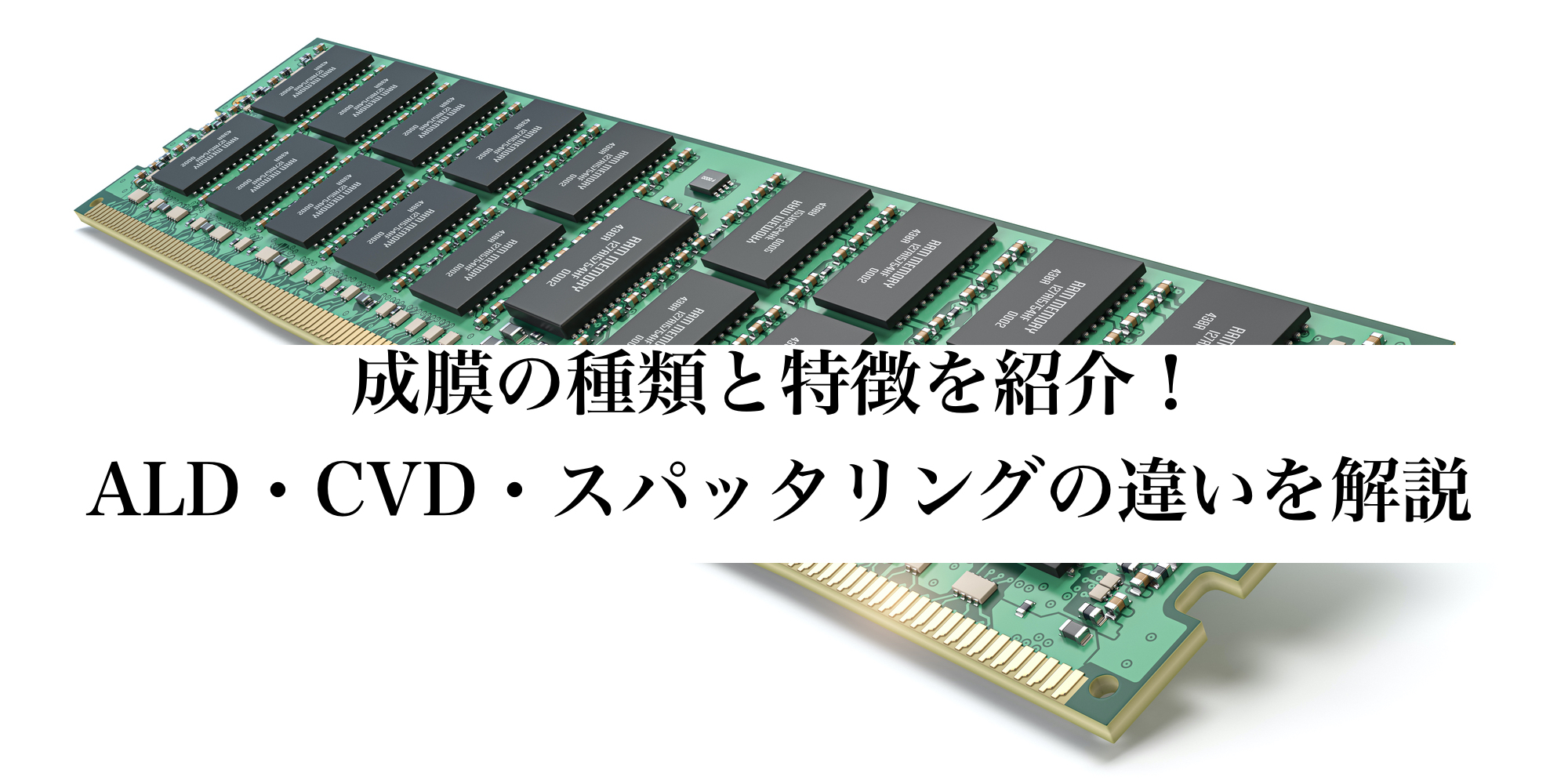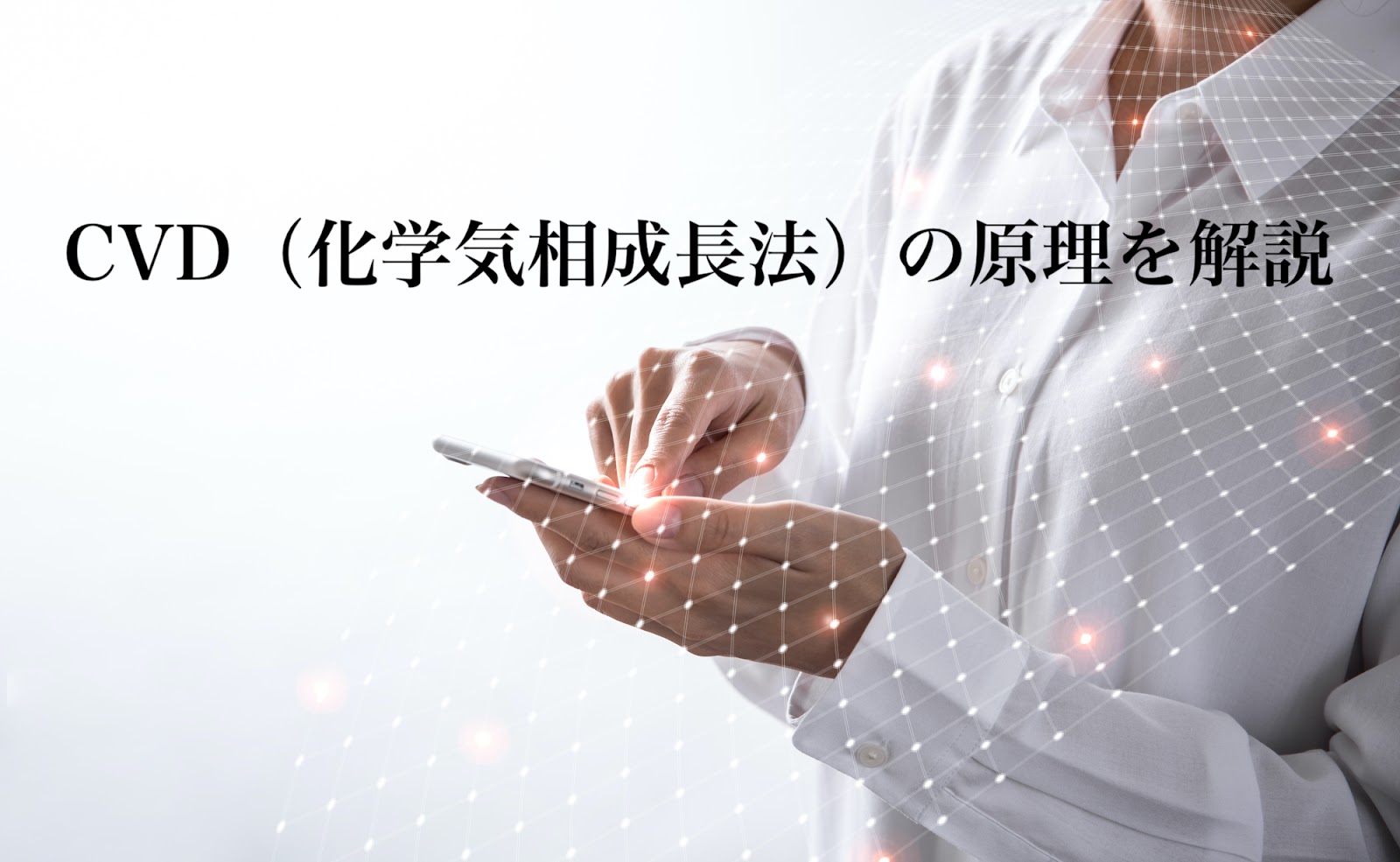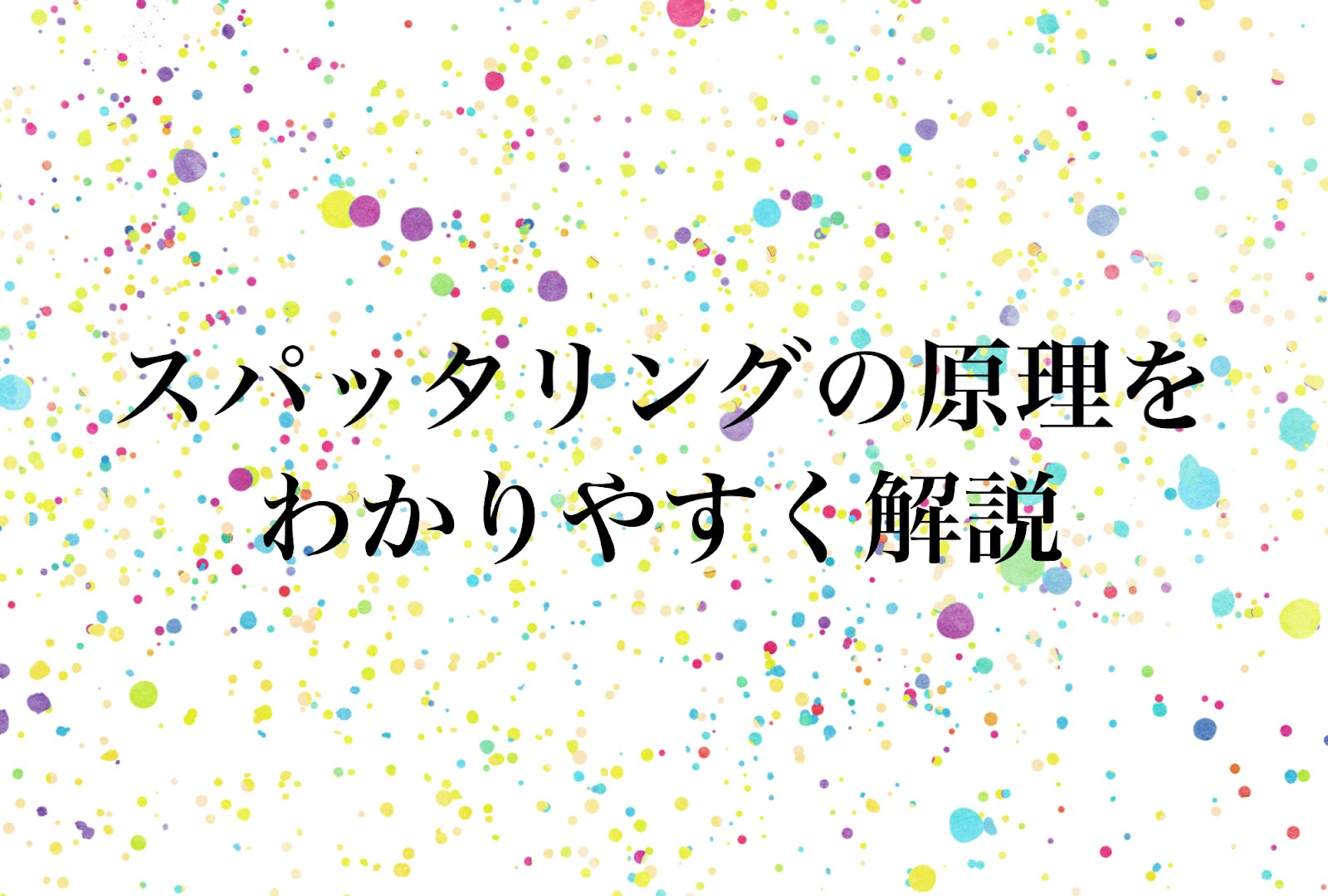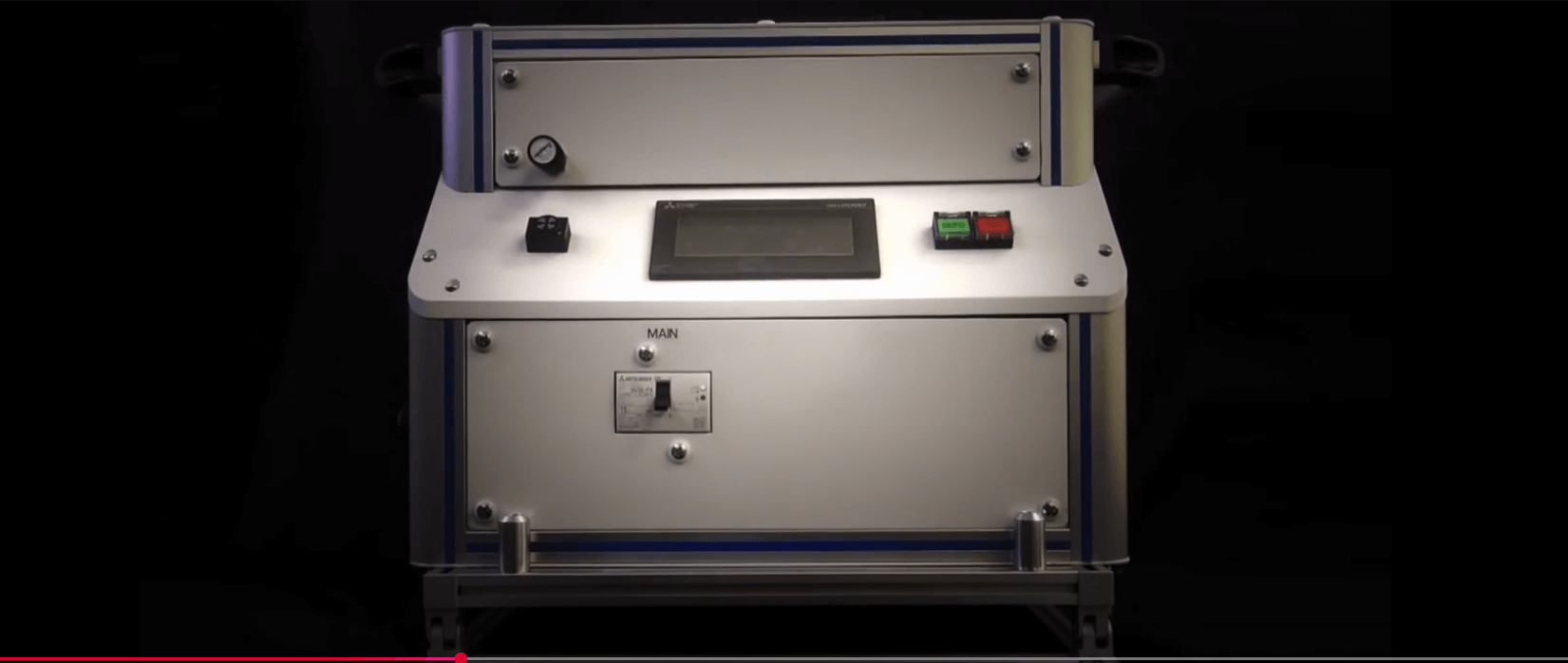私たちの身の回りにある多くの製品には、目に見えないほど薄い膜が施されています。
この薄膜を作る技術を「成膜」といいます。スマートフォンやパソコンのディスプレイ、自動車のボディなど、様々な製品に利用されている成膜について、詳しく解説していきます。
現代のデジタル社会を支える半導体デバイスは、ナノメートルレベルの極めて精密な薄膜が何層も積み重なってできています。
この複雑な多層構造を、設計通りに正確に形成するプロセスこそが「成膜」です。
成膜技術の優劣が、デバイスの性能や信頼性、そして製造コストを大きく左右するため、半導体製造において成膜は最も重要な技術の一つとされています。
本記事では、半導体製造における成膜の役割を掘り下げ、主要な成膜技術とその使い分けについて詳しく解説します。
北海道北斗市に拠点を置く株式会社菅製作所は、独自の技術力を駆使し、幅広い分野で皆様の挑戦をサポートしています。スパッタ装置やALD装置等の成膜装置や光放出電子顕微鏡などの真空装置、放電プラズマ焼結(SPS)による材料合成装置、漁船向け船舶用機器を製造・販売しています。また、汎用マイコン・汎用メモリへの書込みサービスも行っています。どのような研究開発でも一度ご相談ください。菅製作所が独自に培った技術力で皆様の創造をアシストします。
成膜とは
成膜(せいまく)とは、固体表面に薄い膜を形成する技術全般を指します。電子部品や光学部品、工具など、様々な工業製品の機能性向上に不可欠なプロセスです。
特に半導体製造においては、トランジスタや配線、絶縁膜といった多層構造を形成するために極めて重要です。
原子レベルで制御された緻密な膜を均一に基板へ堆積させることが求められます。
成膜技術には、真空蒸着やスパッタリング、そして原子1層ずつ積み重ねるALD(原子層堆積法)などがあり、用途に応じて最適な手法が選択されます。これにより、高性能かつ安定した半導体デバイスの製造が可能となります。
「薄膜」との違いとは
結論からいうと、薄膜はモノ、成膜はコトです。成膜という行為によって、薄膜が作られ、基板の機能が向上します。
【薄膜】
薄膜は、非常に薄い膜そのものを指します。その厚さが数ナノメートルから数十マイクロメートルの非常に薄い層のことです。
この薄膜は、基板の表面に付着させることで、基板の性質を変化させたり、新たな機能を持たせたりすることができます。
例えば、ガラスのコートや金属の表面に付着した保護層などがこれにあたります。
【成膜】
一方で成膜は、その薄膜を作るための行為や工程を指します。
つまり、薄膜を作ることを「成膜する」と表現するのです。
成膜は、真空蒸着、スパッタリング、CVDなど、様々な方法を用いて、基板上に薄膜を形成するプロセスです。
半導体製造における成膜の役割
半導体デバイスは、トランジスタや配線、絶縁膜といった多層構造で成り立っています。これらの微細な層を、設計通りに、そして極めて高い精度で形成するために、成膜技術が不可欠となります。
例えば、トランジスタのゲート絶縁膜がわずかに不均一であるだけで、デバイスの電気特性にばらつきが生じ、製品の歩留まりが大きく低下します。
成膜は、デバイスの電気回路を形成するだけでなく、各層を電気的に分離したり、物理的に保護したりする役割も担っています。
半導体製造で使われる主な成膜技術
半導体製造の現場では、求められる膜の種類や特性、そしてコストや生産性に応じて、複数の成膜技術が使い分けられています。
ここでは、代表的な成膜技術であるCVD(化学気相成長)、スパッタリング、そしてALD(原子層堆積)の特徴と、半導体プロセスにおける役割を解説します。
成膜加工方法の種類
成膜加工とは、基板上に薄膜を形成する技術です。この成膜には、真空蒸着、CVD、スパッタリング、ALD(原子層堆積)など、様々な方法があります。それぞれの方法によって、形成される膜の性質や、適用できる材料が異なります。
| 原理 | 特徴 | 用途 | |
| 真空蒸着 | 材料を加熱して気化 | シンプル、低コスト | ガラス、プラスチック、金属 |
| CVD | 気体原料の化学反応 | 高純度膜、大面積 | 半導体、太陽電池 |
| スパッタリング | イオン衝突による原子飛散 | 高密度、緻密な膜 | 金属膜、絶縁膜 |
| ALD(原子層堆積) | 自己制限的な表面反応 | 極めて高い膜厚制御性、高被覆性、高品質 | 半導体、MEMS、太陽電池 |
真空蒸着
真空蒸着は、真空状態の中で、材料を加熱して気化させ、その蒸気を基板に直接付着させる方法です。まるで鍋に水を沸かして蓋の裏に水滴が付くように、材料を気化させて基板に到達させ、薄膜を形成します。
- 特徴:シンプルな装置で、比較的低コストで成膜できる。
- 用途:ガラス、プラスチック、金属など、様々な基材への成膜に利用される。
CVD(化学気相成長)
CVDは、気体状の原料を基板上で化学反応させて、膜を成長させる方法です。真空蒸着と比べて、より複雑な組成の膜を形成することが可能です。
- 特徴:高純度の膜を形成できる。大面積の基板への成膜に適している。
- 用途:半導体デバイス、太陽電池、ディスプレイなど、高純度な膜が要求される分野で利用される。
スパッタリング
スパッタリングは、ターゲットと呼ばれる材料に高エネルギーのイオンを衝突させ、飛び出した原子を基板に付着させる方法です。真空蒸着と比べて、高密度で緻密な膜を形成できるのが特徴です。
- 特徴:高密度で緻密な膜を形成できる。様々な材料の成膜が可能。
- 用途:金属膜、絶縁膜、導電膜など、幅広い分野で利用される。
ALD(原子層堆積)
ALD(原子層堆積)は、自己制限的な表面反応を利用し、原子1層ずつ薄膜を形成する方法です。この方法により、極めて均一で精密な膜を形成できます。
- 特徴:膜厚の制御性が極めて高い。基板の複雑な形状にも高い被覆性(コンフォーマリティ)があり、段差の内側にも均一な膜を形成で▶きます。
- 用途:半導体デバイスのゲート絶縁膜、高誘電率(High-k)膜など、極めて精密な薄膜が要求される分野で利用される。
菅製作所では「テスト成膜サービス」を行っております
装置の新規導入を前提としたお客様を対象に、弊社保有のデモ機によるシリコンウェハやお客様御支給のサンプルに対するテスト成膜サービスを行っております。
スパッタリング、ALDの成膜を承っております。
お客様がご来社の上、装置本体の説明を含むテスト成膜のコースと、サンプルをお預かりして弊社で成膜する方法の2通りの方法を選択できます。ご要望の条件によっては有償での成膜となりますので一度ご相談ください。
また、弊社装置の導入が前提ではないお客様に対しても有償で成膜を承ります。但し、処理量や膜質への保証について制限がございますのでご相談ください。
成膜にスパッタリングを採用するメリット
菅製作所では、お客様のニーズに合わせてカスタマイズするスパッタ装置を取り扱っております。
そこで以下に、成膜においてスパッタリングを採用するメリットについて詳述します。
①強力な付着力
スパッタリングでは、高エネルギーのイオンがターゲット材料を叩きつけることで、材料の原子を基板に叩き込みます。このため、形成される膜は基板との結合が非常に強く、耐摩耗性や耐久性に優れています。
②緻密で滑らかな膜
スパッタリングで形成される膜は、原子レベルで緻密に積層されるため、表面が非常に滑らかです。この特性は、光学素子や磁気記録媒体など、表面の平滑性が求められる分野で特に重要です。
③幅広い材料に対応
スパッタリングは、材料を加熱して蒸発させる必要がないため、高融点の金属や合金など、従来の方法では難しかった材料の薄膜化も可能です。また、複合材料の薄膜も形成できるため、多様な材料設計が可能になります。
④低温プロセス
基板を高温にする必要がないため、熱に弱い基板や有機材料へのコーティングも可能です。これは、電子デバイスやフレキシブルディスプレイなどの分野で大きなメリットとなります。
⑤均一な膜厚
スパッタリングでは、大面積の基板に均一な厚さの膜を形成できます。これは、特に半導体製造プロセスにおいて重要な要素です。
成膜装置の種類と特徴
成膜装置は、その構造や処理能力によって、様々な種類に分類されます。
それぞれの装置は、基板の形状や成膜したい膜の種類、生産量などに応じて最適なものが選択されます。
①バッチ式(カルーセル型)
- タンク状の装置内に基板をセットし、回転させながら成膜を行う。
- 基板形状の自由度が高く、試作や少量生産に適している。
- スパッタリングや真空蒸着といった様々な成膜法に対応可能。
用途:研究開発、試作、多様な基板形状への成膜
②インライン式
- 基板を連続的に搬送しながら成膜を行う。
- 高い生産性と均一な膜厚を実現できる。
- 自動化による省力化が可能。
用途:大量生産、フラットパネルディスプレイ、太陽電池など
③ロールtoロール式
- ロール状の基板を連続的に搬送しながら成膜を行う。
- 大面積の薄膜を高速で形成できる。
- フレキシブル基板への成膜に適している。
用途:フレキシブルディスプレイ、タッチパネル、太陽電池など
④円筒内面式
- 円筒状の基板の内面に成膜を行う。
- 反射鏡、フィルターなどの機能性薄膜を形成できる。
用途:光学素子、フィルター、センサーなど
成膜加工ができる材料の特性と用途
成膜加工は、様々な材料の表面に薄膜を形成することで、その材料の特性を大きく変えることができる技術です。
| 代表的な材料 | 特性 | 用途 | |
| 金属 | アルミニウム (Al)、銀 (Ag)、金 (Au)、銅 (Cu)、チタン (Ti) など | 高い導電性、熱伝導性、機械的強度 | 合金や複合材料も使用可能で、多様な特性の薄膜が実現できる。 |
| ガラス | シリカガラス | 透明性、耐熱性、化学的安定性 | ディスプレイ、光学レンズ、太陽電池など |
| 樹脂 | ポリエチレンテレフタレート (PET)、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂など | 柔軟性、軽量性、絶縁性 | 包装材、電子部品、光学部品など |
| シリコン | アモルファスシリコン、ポリシリコン | 半導体特性、耐熱性、耐薬品性 | 半導体デバイス、太陽電池、センサーなど |
| セラミック | アルミナ (Al₂O₃)、ジルコニア (ZrO₂) | 高硬度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性 | 切削工具、耐熱部品、生体材料など |
| DLC (ダイヤモンドライクカーボン) | ー | ダイヤモンドに近い硬度、耐摩耗性、潤滑性 | 切削工具、自動車部品、医療器具など |
成膜の流れ
①基板の検査と準備
数量、種類、状態などを確認し、傷や汚れがないか厳重にチェックします。
このとき超音波洗浄などにより、基板表面の汚れを徹底的に除去します。この工程は、後の成膜の品質に大きく影響するため、非常に重要です。
②薄膜形成(成膜)
基板のサイズ、形状、材質、成膜したい膜の種類、生産量などに応じて、最適な成膜装置を選択します。
その後、真空蒸着、スパッタリング、CVDなど、様々な成膜方法を用いて、基板上に薄膜を形成します。
③品質検査
- 外観検査:目視や顕微鏡を用いて、膜の表面状態や外観を検査します。
- 膜厚測定:膜厚計を用いて、膜厚が設計値通りであるかを確認します。
- 特性評価:必要に応じて、膜の電気的特性、光学的特性、機械的特性などを評価します。
成膜とアニール処理
アニール処理は、材料や製品を加熱することで、内部の応力を解放し、より安定した状態にする熱処理の一種です。
成膜加工においては、膜と基板の密着性を高めたり、膜の特性を改善したりするために用いられます。
アニール処理の意義
【膜と基板の密着性の向上】
膜と基板の界面を強固にし、剥がれや割れを防止します。
【残留応力の除去】
加工によって生じた内部応力を解放し、製品の変形やひび割れを防ぎます。
【膜の結晶構造の改善】
膜の結晶構造を最適化し、電気的特性や機械的特性を向上させます。
【不純物の除去】
膜中に残留する溶剤や不純物を揮発させ、膜の純度を高めます。
まとめ
成膜は、素材に新たな機能を与えることができる、非常に重要な技術です。真空蒸着、CVD、スパッタリングなど、様々な方法がありますが、それぞれ特徴があり、用途も異なります。今後も成膜技術は、より高度化し、私たちの生活をさらに豊かにするでしょう。
【参考】
『成膜の基礎』京都大学
『成膜技術でよく使われるスパッタリング!その原理と方法5つについて徹底解説』ジオマテック
『成膜加工の基礎知識』Seimaku Navi